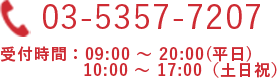離婚という言葉は、一般的にはマイナスのイメージのほうが強いかもしれません。
確かに、離婚の話し合いは、楽しいものではないでしょうし、決めなければならないことも多く、離婚後の生活に不安を感じることも多いはずです。
離婚という言葉に抵抗を感じたり、人の目が気になってしまうこともあるかもしれません。
離婚を決断することに、罪悪感を感じることもあるようです。
離婚したいという希望を持ちつつも、自分の我慢が足りないのでは?と悩んでいる方もいます。
でも、人は、誰でも幸せになる権利があります。
離婚を選ぶということは、今よりも幸せになるために、勇気をもってハードルを越えることとも言えると思います。
弁護士が、離婚を薦めることはありません。
離婚するかどうかを判断できるのはご本人だけです。
ただ、結婚生活の中で幸せを感じることができなくなった時に、離婚という選択肢があることを知っておくことは大切だと思います。
離婚という選択肢があると考えるだけで、心に余裕が生まれて、もう少しがんばって結婚を続けてみよう、と思うこともあるようです。
調停の中で、たまに、調停委員が「評議します」と述べることがあります。
これは、調停委員が、担当裁判官と話し合いをしたり、裁判官に意見や助言を求めることです。
調停が成立する場合や不成立となる場合は、まず調停委員が裁判官と評議した上で、裁判官が決めます。
その他、双方の主張が平行線である場合に、どうすべきかについて、裁判官と評議して助言を求めることで、話合いが進むことがあるのです。
評議の結果、調停委員から「裁判官がこのように言っているので、あなたの主張は通らないのでは?」等と言われることもあるかもしれません。
裁判官の見解を前提にせざるを得ないことが多いと思いますが、注意すべきなのは、調停委員から裁判官に対して情報が正しく伝わっていない場合があり得ることです。
また、争点(意見が食い違う点)によっては、裁判官によって意見が異なる場合もあります。
さらに、裁判官も、調停段階であるという前提で、解決案の提案という趣旨で、訴訟での判断とは、異なる解決案を提案することもあります。
評議の結果にどうしても納得できない場合は、あきらめずに、弁護士等に相談してどうすべきかを考えることをお勧めします。
なお、「裁判官の見解」はそれなりの重みがあるため、離婚事件の経験がかなり豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
経験上、裁判官と直接話をした結果、風向きが変わったこともありますし、調停での解決をあきらめて、訴訟した結果、こちらの主張が認められたこともあります。
この「評議」のために、待合室で長時間待たされることがありますが、「評議」が長時間行われているのではなく、裁判官を待っている時間がほとんどの場合があります。
裁判官は、多くの事件を担当しているため、複数の部屋から呼ばれていることが多いため、「評議」を求めても、なかなか部屋に来られないことがあるためです。
人には相性がありますので、調停委員と合わない場合もあると思います。
また、正直、調停委員の経験や離婚に関する知識等に疑問を感じたり、価値観の偏りを感じる例もあるようです。
時には、調停委員が先方ばかりに味方して、自分には味方してくれないと感じる場合も多いようです。
実際、調停委員によって、調停の進め方や雰囲気がかなり異なります。
調停委員と合わないな、と感じる場合でも、自分の意見や考えをしっかりと伝えて、納得できない場合は、調停を成立させないことが大切です。
「この内容に応じないなら不成立になって、裁判になりますよ」等と言われ、慌てて成立させてしまったと言われることがよくあります。
中には「裁判したら、もっと不利になりますよ」等と言われて、調停を成立させてしまう場合もあるようです。
私の経験でも、根拠なく先方が、なんの根拠も示さずに提案した和解案について「根拠が示されていないので応じません」と断ったところ、調停委員から「どうして応じないのですか?」等と追及され、驚いたこともあります。
調停は一度成立させてしまうと、後で変更することはできなくなります。
繰り返しますが、何より大切なのは、納得できない場合は成立させないことです。
「応じないなら不成立になります」等と言われても、「次回まで検討したい」「次回まで検討する時間がほしい」と述べて、とりあえず時間をもらうようにしましょう。
そのうえで、検討した結果、納得できるのであれば次回に成立させれば済むことですし、納得できないのであれば、対案を出したり、不成立やむなしとする等の方針を考える必要があります。
弁護士がいない場合は、一度弁護士に相談した上で、成立させるかどうかを考えることを強くお勧めします。
離婚調停は、実質的に男女2名の調停委員が話し合いを仲介する形で、話し合いが行われます。
1回の時間は、1時間30分から2時間程度で予定されています。
一般的な流れは、まず申立人側が調停室に入室して、調停委員と30分程度話し、次に相手方側が入室して30分程度話す、というのが2回程度繰り返される形です。
ただ、実際は、話合いの内容や状況によって様々です。
最初に、調停委員が、調停制度について説明してくれますので、もし弁護士がいない場合は、よく聞いて、わからないことがあれば、遠慮なく確認するといいと思います。
調停委員は、話合いの仲介をしてくれるだけなので、例えば、離婚すべきかどうかなどを判断することはありません。
そういう意味では、調停委員を味方につけても、有利な条件での離婚につながるとは限りません。
ほとんどの調停委員の方々は、双方が納得して離婚問題を解決することができるよう協力しようとしてくれるはずです。
したがって、調停委員との間に一定の信頼関係を築くことができると、こちらの意図をきちんと汲み取って、相手に丁寧に伝えてくれたり、裁判官に相談して、最良の解決法について一緒に考えてくれることがあります。
まずは、リラックスして、調停委員に自分の気持ちや希望する解決内容などを率直に伝えてみるといいと思います。
相手に伝えてほしくないことなどは「これは相手には伝えないでほしい」と言えば、相手に伝わることはないはずです。
調停委員の理解を得られた結果、調停委員が相手サイドを説得してくれたおかげで、調停で解決することができることもあります。
2025.08.19
離婚調停の申立書が届いた場合 ②
離婚調停を申し立てられた場合、裁判所から届く書類の中に、答弁書が入っており、申立書に対する意見は反論等を記載して提出するよう、記載があることがあります。
これは、話合いをスムーズに進めるために、裁判所側で予め話合うべき内容を把握しておくためのものと考えられます。
答弁書を裁判所に提出すると、申立人が裁判所で手続きすることで、答弁書の内容を見ることができます。
したがって、答弁書は、申立人が見るかもしれないということを前提に書く必要があります。
※ もし、離婚条件などで、揉めてしまう可能性があるときは、この時点で弁護士に相談することをお勧めします。
答弁書に何を書いていいのかわからない場合で、弁護士に相談することもできない場合は、裁判所に連絡して、答弁書を出すことができないと相談してみてもいいと思います。
裁判所次第ではありますが、調停は話し合いですので、予め答弁書を提出することができなくても、期日に口頭でご自身の意見を説明することで、調停を進めることが可能です。
いずれにしても、紙に書いて提出する、ということは、後に客観的な証拠となる可能性がありますので、答弁書の記載内容については、慎重に考えることをお勧めします。