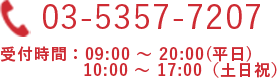相手に不倫や暴力等があるわけではないけど、これ以上一緒に暮らしていくのが難しい、という心境に陥っている方からご相談を受けることがあります。
いわゆる「性格の不一致」です。
実際に、離婚する原因で最も多いのは「性格の不一致」と言われています。
夫婦双方が、性格の不一致を感じて離婚を希望している場合は、条件さえ決まればスムーズに離婚できますが、片方のみが性格の不一致を感じている場合は、スムーズに離婚できないことがあります。
同居期間に比べて別居期間が長期になっていると、比較的離婚が認められやすい傾向にありますが、別居期間が短い場合は、「性格の不一致」だけでは、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認めてくれず、棄却されてしまう可能性があるのです。
すなわち、相手のモラルハラスメントによって離婚を希望している場合でも、証拠が足りない場合は、単なる性格の不一致とみなされて、離婚が認められないことがある一方で、片方による一方的な別居であっても、別居期間が長期化すると、離婚が認められる傾向にあるのです。
裁判所の対応に関して、柔軟性が欠けるのでは?と感じることもありますが、第三者が判断する以上、一定のルールに基づいて判断する必要があるため、仕方ない部分があるのかもしれません。
いずれにしても、「性格の不一致」だけが理由でも、離婚できないわけではありません。
もし、こんなことで離婚できるのかな?という悩みがある場合は、あきらめずに、是非相談してみていただければと思います。
「別居したいけど相手の了承が得られない」「同居義務違反や悪意の遺棄になってしまうのでは?」との相談を受けることがあります。
確かに、同居義務は民法752条に明記されています。
またインターネット等の情報を見ると、「悪意の遺棄」という言葉をよく目にします。(悪意の遺棄とは、夫婦間の同居、協力、扶助の義務を、正当な理由なく意図的に履行しないことです)
実際は、正当な理由があれば、相手の了承なく別居することは可能ですし、「悪意の遺棄」に該当することもありません。
離婚事件では、離婚を希望する側が別居した上で離婚を請求することがよくあります。
その際、相手の了承を得ていないことがほとんどですが、離婚訴訟などで、それが問題となることは、経験上はほとんどありません。
住み慣れた家を出て、わざわざ別居する場合は、それなりの理由があることがほとんどです。
以前、モラハラを原因として慰謝料が認められるためのハードルが高いという内容を書きましたが、「同居義務違反」や「悪意の遺棄」による慰謝料が認められるためのハードルも相当高いと言えます。
ただ、例えば、相手に落ち度がないのに不倫した上で突然出ていくとか、幼い子がいる専業主婦を置いて突然出て行き、生活費も払わない等の行為は、問題となる可能性があります。
モラハラを受けたので、慰謝料を請求したいというご相談を受けることがあります。
確かに、モラハラは他人を傷つける行為ですので、法律上の不法行為になり得る行為です。
しかし、モラハラを原因として慰謝料が払われる例は、実際はかなりレアケースです。
理由は、① 証明が難しく、② 相手が自ら慰謝料を払うことがほとんどないからです。
① については、日々のモラハラ的な言動を、客観的に証明するのはかなり難しいです。
具体的に主張しても、相手からは、予測をはるかに超える反撃(反論)がなされることも珍しくありません。
相手の反論のすべてが嘘だとしても、第三者である裁判官から見ると、どちらかの言い分だけを事実として認めることができないことがほとんどです。
②については、相手が「モラハラをしたので慰謝料を払う」と言ってくれることは、まずありません。
モラハラをする人は、自分の言動が正しいと思っている人がほとんどです。
なので、慰謝料を払わせるには話し合いや調停では難しく、離婚訴訟で慰謝料を勝ち取るしかありません。
ほとんどの方は、認められるかどうか分からない慰謝料を求めて訴訟するよりも、話し合いや調停で早く解決することを選びますので、モラハラの慰謝料が問題になること自体も少ないのが現実です。
したがって、モラハラを受けたからといって、慰謝料が払われる、ということにはならないことが多いと感じます。
ただ、離婚問題は、本当に様々ですので、実際は具体的な事情次第です。
また、担当する裁判官次第で、慰謝料の可否、金額が変わることもあります。
「夫(妻)の言動はモラハラですか?」という質問を受けることがあります。
「モラルハラスメント(モラハラ)」は法律用語ではないため、どこまでいけばモラハラに該当するかということは、はっきりしていません。
問題なのは、相手の言動が「モラハラ」かどうかではなく、相手から「モラハラを受けている」と感じたり、結婚生活に辛さを感じることです。
「もう少し我慢すべきと思うけど」等とおっしゃる方も少なくありません。
結果的に、経済的な面を優先して離婚を先延ばしにすることを選択せざるを得ない場合もあると思います。
でも、結婚生活は、我慢したり、がんばって継続するようなものではないはずです。
モラハラをする人は、絶対的に自分が正しいという前提で話をするため、モラハラを受ける側は、自分が悪いのでは?と感じてしまう傾向があります。
自分の心に生まれた疑問やマイナスの感情を無視せず、しっかり向き合うことが大切です。
夫婦関係に疑問を感じたら、まずは信頼できる友人や親類に相談して、客観的な意見を聞いてみるのもひとつです。
真面目な方ほど、辛さを心に秘めていたり、離婚をあきらめている方が多いようです。
どうか、一人で悩まず、相談してみてください。
離婚だけが選択肢ではなく、まずは別居するという方法もあります。
モラルハラスメントと検索すると、「言葉や態度などで相手の尊厳を傷つけ、精神的に苦痛を与える嫌がらせ行為」等との説明があります。
夫婦間でも問題になることが多く、夫や妻による言動に苦しんでいる方は少なくありません。
中には、ギリギリまで耐えた結果、体調を崩していたり、心療内科に通っている方もいらっしゃいます。
体調を崩してしまうまで我慢する理由は、離婚という選択肢自体を思いつかないことや、離婚に対するハードルが高いこと、離婚に対するマイナスイメージなどがあるようです。
結婚は、我慢して続けるべきものではないと思います。
もし、結婚が負担であれば、離婚を選択することは間違いではありません。
ただ、弁護士が「離婚した方がいいですよ」などと気軽に言うことはできません。
離婚するかどうかを決めることができるのはご自身です。
問題は、「不倫も暴力もないから、離婚なんかできない」「離婚してもお金は一切渡さない」等と言われて、あきらめている方がいることです。
決してそんなことはありません。
結婚生活に幸せを感じられない方、苦しいと感じている方は、どうか、我慢しすぎないで、早めに相談してみてください。
結婚生活に限界を感じる場合は、離婚という選択肢があること、他にも生きる道があることを心に留めておくことは大切だと思います。